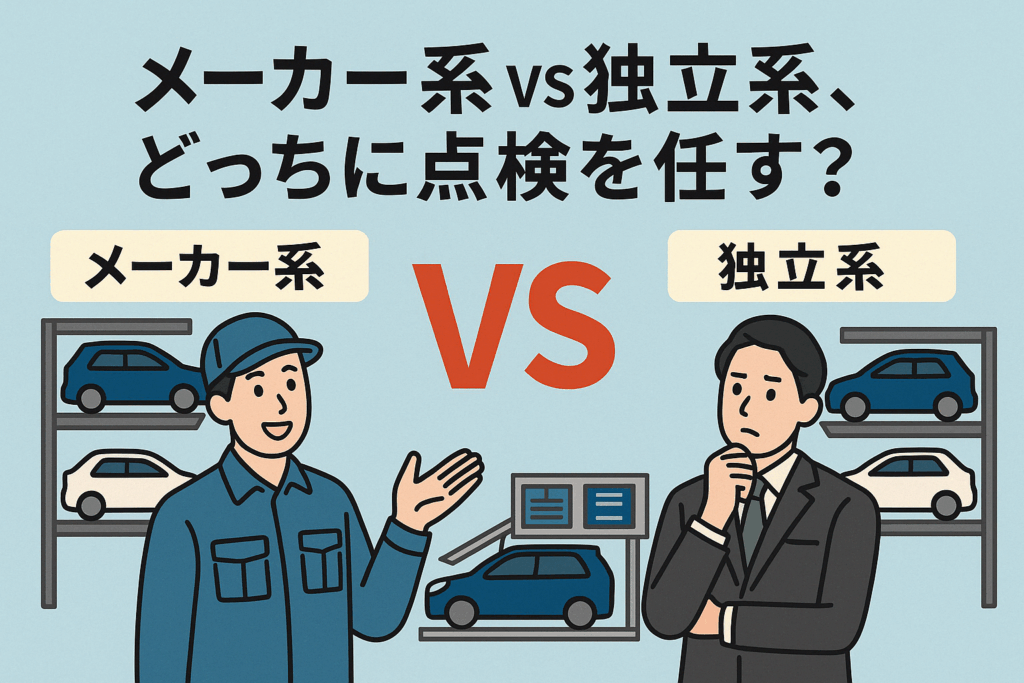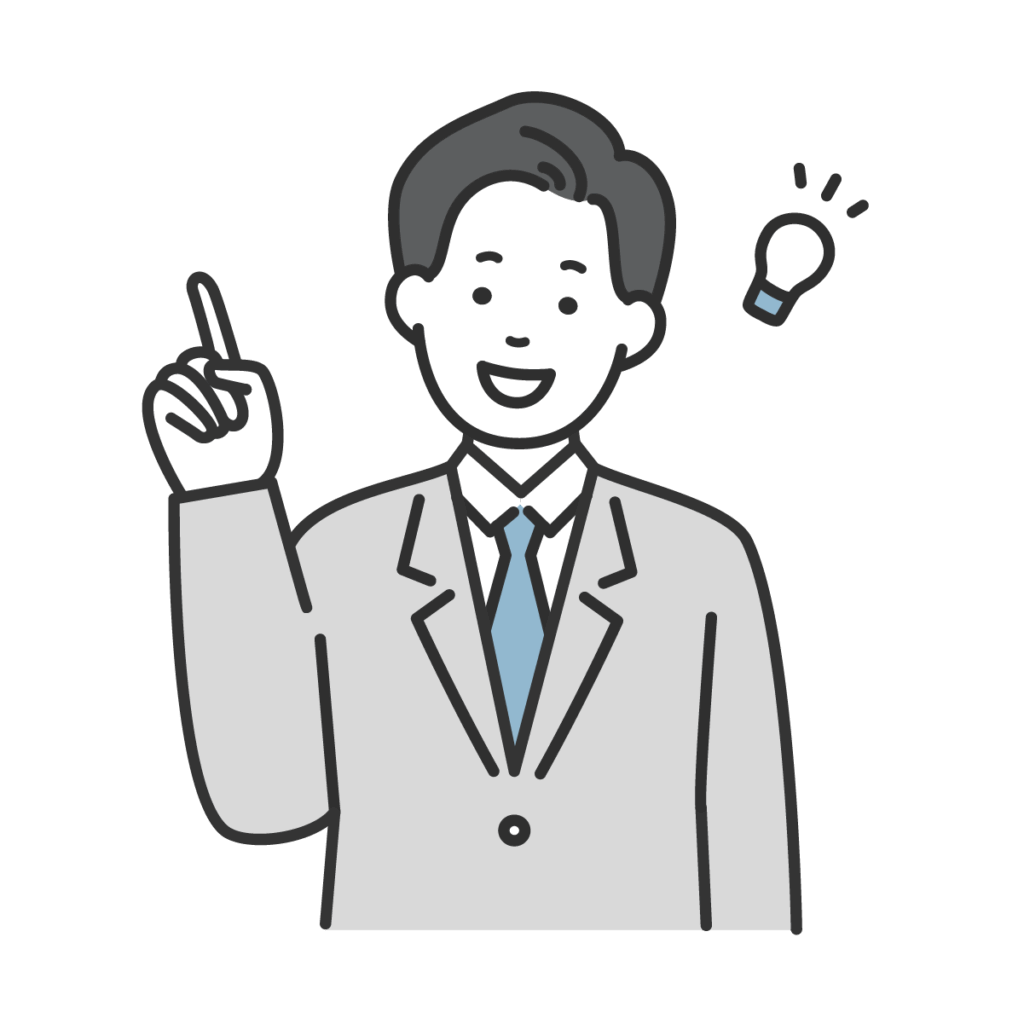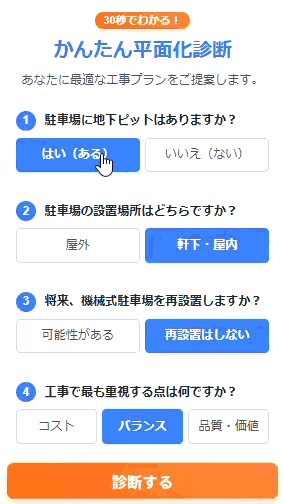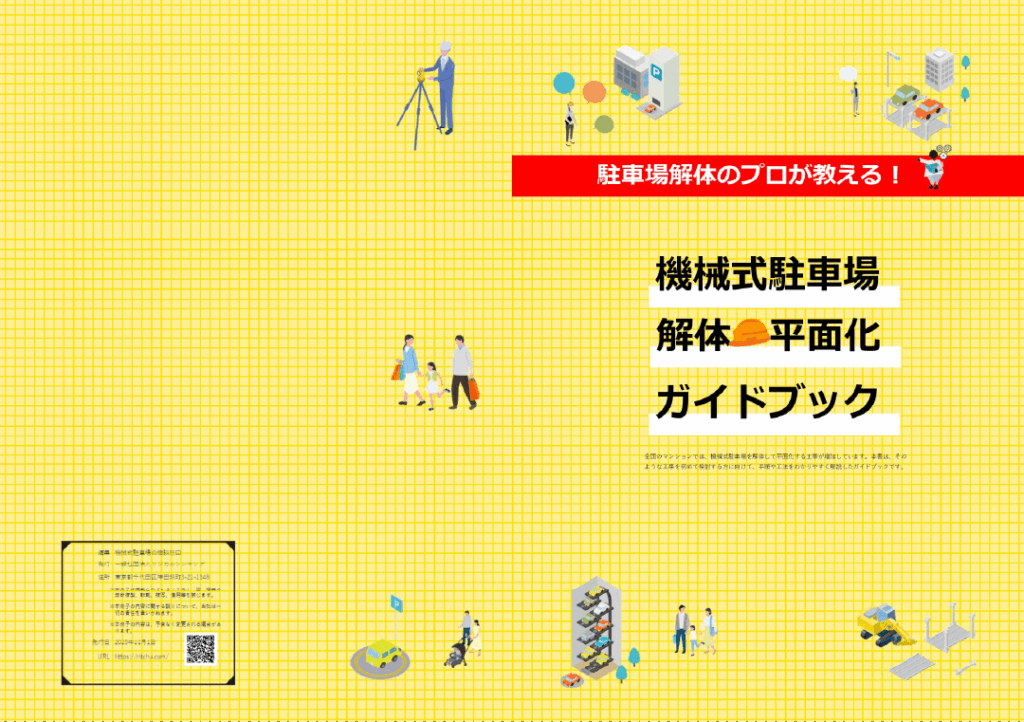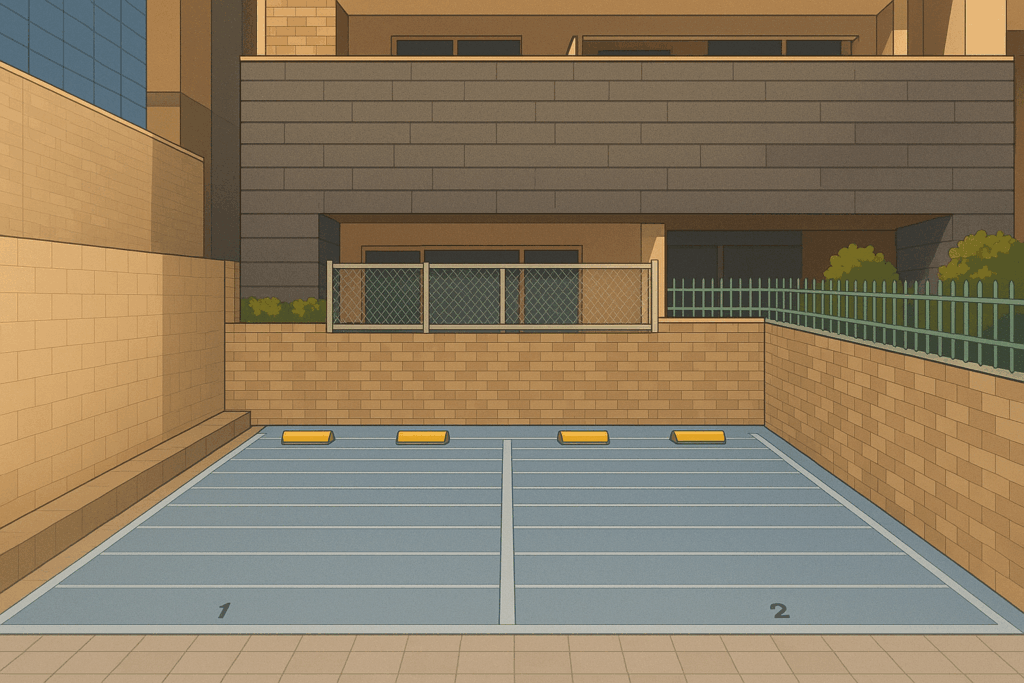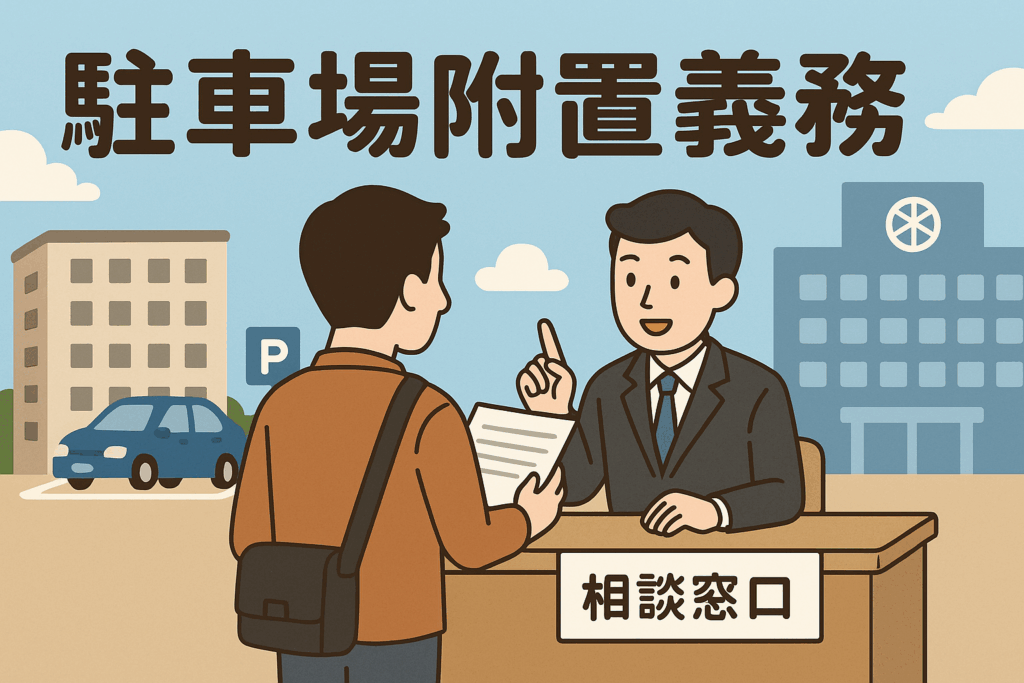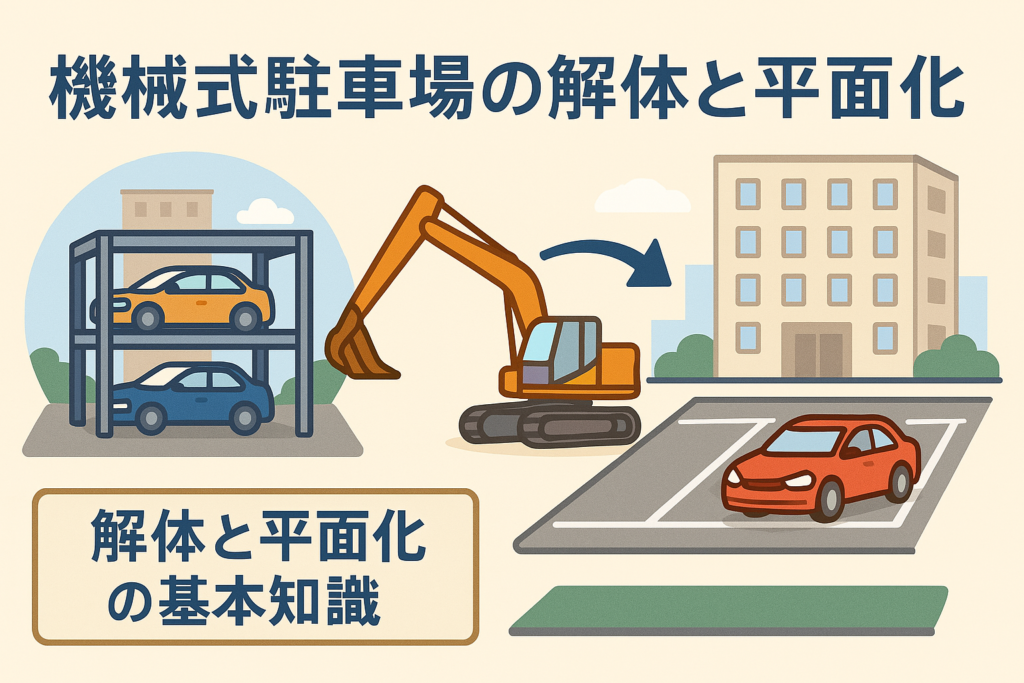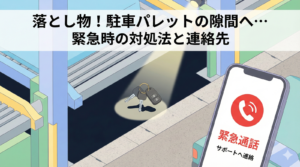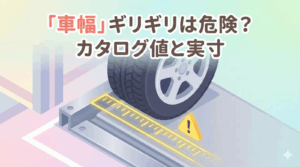マンションの長期修繕計画において、機械式駐車場のメンテナンスは非常に重要ですが、その中でも「パレット(車両を載せる鉄板)の塗装」は、見落としがちな項目の一つです。
「まだ大丈夫だろう」「車を停めるだけだから」と先送りにしていると、ある日、理事会に「パレット腐食による動作不良の報告」や「高額な緊急補修の見積書」が届くことになりかねません。
パレットの塗装工事は、設備の規模にもよりますが、7年~10年に一度、数百万円規模の費用が発生する「大規模修繕」の一つです。しかし、その見積書は専門用語が並び、どこをチェックすれば良いか分かりにくいのも事実です。
この記事では、マンション管理組合の理事やオーナー様に向けて、機械式駐車場のパレット塗装工事で後悔しないために、見積書を精査する具体的なポイントから、適切な業者選定、コスト構造の裏側まで、専門家の視点で徹底的に解説していきます。
- 1. 【基礎知識編】なぜパレット塗装は不可欠なのか?
- 1.1. 放置された「錆」が引き起こす3大リスク
- 1.2. パレットの仕上げとメンテナンス周期
- 1.3. 劣化を早める「要注意」環境
- 2. 【業者選定編】どこに頼むのが正解か?
- 2.1. なぜ「外壁塗装業者」ではダメなのか?
- 2.2. 依頼先候補となる業者の種類と特徴
- 2.3. 信頼できる業者か? 見極めのチェックリスト
- 3. 【コスト編】管理会社経由の見積はなぜ高いのか?
- 3.1. 重層下請け構造と中間マージン
- 3.2. 中間マージンが引き起こす「品質の低下」
- 3.3. コストと品質を両立させる「分離発注」という選択肢
- 3.3.1. 対策:業者の「リプレイス」も視野に
- 4. 【見積書チェック編】後悔しないための10の確認ポイント
- 4.1. 下地処理:「ケレン作業」の具体的手法
- 4.2. 錆の処理:「錆転換剤」の使用の有無
- 4.3. 塗装回数:「3回塗り」が基本
- 4.4. 使用塗料①:「樹脂の種類」は適しているか
- 4.5. 使用塗料②:「1液式」か「2液式」か
- 4.6. 使用塗料③:「メーカー名」と「製品名」
- 4.7. 安全性:「防滑(ぼうかつ)仕上げ」の有無
- 4.8. 洗浄:「高圧洗浄」の工程
- 4.9. 工程管理:「工区」と「養生(乾燥)時間」
- 4.10. 諸経費:「一式」の中身
- 5. 【将来計画編】塗装以外の選択肢も視野に入れる
- 5.1. 塗装不可能な状態の見極め
- 5.2. 選択肢①:パレット交換
- 5.3. 選択肢②:装置全体の更新(リニューアル)
- 5.4. 選択肢③:解体・平面化
- 6. まとめ
- 6.1. 見積書チェックの最終確認リスト
【基礎知識編】なぜパレット塗装は不可欠なのか?
まず、なぜパレットの塗装が「美観」以上の重要な意味を持つのか、その理由と基礎知識を深く掘り下げます。
放置された「錆」が引き起こす3大リスク
パレットの錆は、塗膜(塗装の膜)が紫外線や雨、タイヤとの摩擦で劣化し、剥がれた箇所から鉄部がむき出しになることで発生します。この錆を放置すると、連鎖的に様々な問題を引き起こします。
リスク1:騒音・動作不良
錆が進行すると、パレットの表面が膨張したり、部材同士のクリアランス(隙間)が不均一になったりします。これにより、パレット昇降時や横行時に「ガガガ」「キー」といった異音が発生し始めます。これは単にうるさいだけでなく、機械に余計な負荷がかかっているサインであり、モーターやギアの故障原因にもなります。
リスク2:車両の汚損(錆汁)
最も居住者クレームに直結しやすい問題です。パレットに溜まった雨水や結露が錆を溶かし、「錆汁(さびじる)」となって駐車中の車両(特にボンネットや屋根)に滴り落ちます。 この錆汁は単なる汚れではなく、鉄イオンを含んだ酸性の液体です。車の塗装面に付着すると、時間経過とともに塗膜に侵食し、洗車やコンパウンド(研磨剤)でも落ちない深刻な「シミ」を残すことがあります。
リスク3:重大事故の誘発
最も恐ろしいのが、腐食によるパレットの強度低下です。錆は表面だけでなく、鉄板の内部(厚み方向)にも進行します。 長年放置されたパレットは、見た目以上に鉄板が薄くなっていることがあり、最悪の場合、車両(1.5トン~2トン)の重量に耐えきれず、パレットが変形・破損し、車両が転落・巻き込まれるといった重大事故につながる恐れがあります。
パレットの仕上げとメンテナンス周期
パレットの表面仕上げには、主に2つの種類があり、これによって耐久性とメンテナンス周期が大きく異なります。
| 仕上げ方法 | 特徴 | 耐用年数(目安) | メンテナンス |
|---|---|---|---|
| 塗装仕上げ | 鉄板の上に直接、防錆塗料や上塗り塗料を塗布する方式。初期コストが安い。 | 約7〜10年 | 定期的な再塗装が必須。 |
| 溶融亜鉛めっき | 鉄板を、高温で溶融した亜鉛の槽に浸し、表面に強固な亜鉛の膜を形成する方式。 | 約15〜20年以上 | 原則として再塗装は不要。ただし傷からの錆は発生しうる。また、沿岸部(塩害地域)では亜鉛の消耗(犠牲防食)が早まるため、定期的な点検(めっき層の残存確認)が推奨されます。 |
多くの築年数が経過したマンションでは、建設時の初期コストを抑えるため「塗装仕上げ」が採用されているケースが一般的です。 「溶融亜鉛めっき」は、亜鉛が鉄より先に錆びる(犠牲防食)ことで鉄本体を守るため、非常に高い防錆効果を発揮しますが、コストは高くなります。
※注意:耐用年数はあくまで目安です
実際の耐久性は、施工品質、下地処理の丁寧さ、そして後述する環境条件によって大きく変動します。定期的な点検による劣化状態の把握が重要です。
劣化を早める「要注意」環境
塗装の耐用年数はあくまで目安です。以下の環境下では、劣化が著しく早まるため、より早期の点検とメンテナンスが求められます。
- 海沿いの立地(塩害):
潮風に含まれる塩分が、塗膜の劣化と鉄の腐食を強力に促進します。 - 寒冷地(融雪剤):
道路に撒かれる融雪剤(塩化カルシウム)を付着させたタイヤがパレットに載ることで、塩分が直接持ち込まれます。 - 地下ピット・屋内型:
意外かもしれませんが、風通しが悪く湿気がこもりやすいため、常にパレットが湿潤状態になり、錆が進行しやすい環境です。 - 日当たりが悪い:
紫外線による塗膜の劣化は少ないものの、湿気が乾きにくいため錆の温床となります。
【業者選定編】どこに頼むのが正解か?
「塗装工事なら、出入りの業者でいいか」と安易に決めると、大きな失敗につながります。機械式駐車場の塗装には、特有のノウハウが必要です。
なぜ「外壁塗装業者」ではダメなのか?
管理組合の理事会では「コスト削減のために、大規模修繕の外壁塗装と一緒に、地元の塗装業者に頼もう」という意見が出ることがあります。しかし、これは非常に危険な選択です。
- 「機械」への理解不足:
機械式駐車場は、単なる「鉄の箱」ではなく、精密な制御機器の集合体です。センサー、リミットスイッチ、配線類など、塗料が飛散してはいけない箇所が無数にあります。外壁塗装の感覚で養生(マスキング)を行うと、これらの機器を塗料で汚損・故障させ、取り返しのつかない動作不良を引き起こす可能性があります。 - 塗料の選定ミス:
外壁用の塗料は「耐候性(紫外線への耐性)」を重視しますが、パレット用塗料は「耐摩耗性(タイヤの摩擦)」「耐薬品性(オイル漏れ)」「防滑性(滑り止め)」が求められます。この選定を誤ると、数ヶ月で塗装が剥がれることになります。 - 安全管理・工程管理の違い:
パレットの塗装は、住民の車両利用を制限しながら行う特殊な工事です。車両の移動、工区の設定、乾燥時間の管理など、住民の動線を考慮した工程管理ノウハウがなければ、現場は混乱し、クレームが多発します。
依頼先候補となる業者の種類と特徴
では、どこに依頼すべきか。主な依頼先候補は以下の3つです。
メーカー系メンテナンス会社
- 特徴: 駐車装置の製造メーカー系列の保守会社。
- メリット: 装置の構造を熟知しており、機械の保守と塗装を一括で任せられる安心感がある。
- デメリット: 塗装工事自体は下請けの塗装業者に再発注(丸投げ)することがほとんど。そのため、中間マージンが発生し、コストは最も高額になる傾向がある。
独立系メンテナンス会社
- 特徴: メーカー系列に属さない、独立資本の保守会社。
- メリット: メーカー系に比べて柔軟な対応ができ、コストも安い傾向がある。
- デメリット: 会社によって技術力や塗装工事のノウハウに差が大きい。メーカー系と同様、結局は下請けに発注するケースが多い。
機械式駐車場「専門」の塗装・補修業者
- 特徴: 塗装業者の中でも、機械式駐車場や立体駐車場の施工に特化した専門業者。
- メリット: 専門知識と施工実績が豊富。中間マージンが発生しない「直接発注」が可能なため、コストを大幅に抑えられる可能性がある。
- デメリット: 管理組合が自ら探し、直接やり取りする必要があるため、選定や管理の手間がかかる。機械の保守点検は別途必要。
信頼できる業者か? 見極めのチェックリスト
相見積もりを取る際、業者が信頼できるかを見極めるには、以下の質問を投げかけてみましょう。
- 「機械式駐車場の塗装実績(直近3年分)を見せてください」
「塗装工事の実績」ではなく、「機械式駐車場の」実績であることが重要です。可能なら、どのマンションで、何台規模の工事を行ったかまで確認します。 - 「今回の駐車場(屋外・地下など)に適した塗料の仕様書と、その選定理由を説明してください」 「ウレタンです」「エポキシです」という回答だけでなく、「なぜ、この環境に、このメーカーの、この製品(例:2液式エポキシ樹脂塗料)が最適なのか」を論理的に説明できるかを見ます。
- 「住民への告知や、工事中の車両制限の計画案はありますか?」
「掲示物やポスティングの原案作成を手伝ってくれるか」「工区を分けて、利用制限を最小限にする工夫はあるか」など、管理組合の運営に寄り添う姿勢があるかを確認します。 - 「理事会や総会での説明会に出席してもらうことは可能ですか?」
住民への説明責任を一緒に果たしてくれる業者は信頼できます。
【コスト編】管理会社経由の見積はなぜ高いのか?
理事会に提出される見積書の多くは、管理会社を経由しています。しかし、その金額には「カラクリ」が潜んでいることが多く、注意が必要です。
重層下請け構造と中間マージン
パレット塗装工事は、以下のような重層的な発注ルートをたどることが一般的です。
管理組合(発注者) ↓ マンション管理会社(元請) 【マージン①:10~20%】 ↓ メンテナンス会社(下請) 【マージン②:10~20%】 ↓ 専門の塗装業者(孫請) 【工事実行】
この構造では、管理組合が支払う工事費のうち、実に20%~40%が中間マージンとして、実際の工事を行わない上位の会社に支払われている可能性があります。
例えば、300万円の見積書でも、実際に工事を行う孫請業者の予算は180万円~210万円しかない、というケースも起こりえます。
中間マージンが引き起こす「品質の低下」
問題は、単に価格が高いことだけではありません。 孫請の塗装業者は、限られた(中抜きされた後の)予算内で利益を出さなければなりません。
その結果、「見えない部分」で手抜き工事が行われるインセンティブが働くことになります。
- 最も時間をかけるべき「下地処理(ケレン)」を簡略化する。
- 塗料の使用量を減らす(薄く塗る)。
- 指定された塗料より安価な、低グレードの塗料を使う。
こうした手抜きは、施工直後は分かりませんが、2~3年後に「塗膜が早くも剥がれてきた」「錆が再発した」という最悪の形で現れます。
コストと品質を両立させる「分離発注」という選択肢
この問題を解決する最も有効な手段が「分離発注」です。 これは、管理会社やメンテナンス会社を介さず、管理組合が(あるいは管理会社のサポートのもと)、「機械式駐車場専門の塗装業者」に直接発注する方式です。
- メリット:
中間マージンがすべてカットされるため、劇的なコストダウン(20~40%減)が期待できます。また、浮いた予算を品質向上(より良い塗料を使う、下地処理を丁寧に行う)に回すことも可能です。 - デメリット:
業者の選定、契約、工事監理などを、理事会が主体的に(またはコンサルタントを雇って)行う必要があります。万が一の不具合の際、責任の所在が「塗装」にあるのか「機械」にあるのか、切り分けが難しくなる場合があります。
対策:業者の「リプレイス」も視野に
上で解説した「分離発注」はコスト削減に非常に有効ですが、現在の保守点検業者がメーカー系の場合など、「外部の業者が塗装工事を行うことを許可しない」「非協力的である」といったケースも残念ながら存在します。
そのような場合は、いっそのこと独立系の点検業者へ乗り換える(リプレイスする)ことも検討に値します。独立系は大手メーカー系に比べて柔軟な対応(分離発注の許容など)が可能な場合が多く、点検費用そのものも安くなる傾向があります。
長期的なコストダウンにもつながるため、今回の塗装工事を、保守点検契約のあり方全体を見直す良い機会として捉えることも重要です。
関連記事
メーカー系 vs 独立系、どっちに点検を任す?マンションの機械式駐車場メンテナンス会社の比較ガイド
マンション管理組合向けに、機械式駐車場の点検業者をメーカー系と独立系で比較。特徴・価格・選び方のポイントを解説します。
【見積書チェック編】後悔しないための10の確認ポイント
以下の10項目が具体的に記載されているか見積書をチェックしてください。
下地処理:「ケレン作業」の具体的手法

塗装の寿命は「下地処理(ケレン)で9割決まる」と言われるほど最重要項目です。 NG例:「下地処理 一式」「ケレン清掃 一式」 これでは、何をするのか全く分かりません。必ず、サビの状況に応じたケレンの「種別」が明記されているか確認します。
- 3種ケレン(動力工具・手工具併用):
ワイヤーブラシやディスクサンダー(電動工具)、スクレーパー(手工具)で、浮き錆や古い塗膜を活きている塗膜(密着している部分)は残して除去する方法。機械式駐車場では最も一般的です。 - 2種ケレン(動力工具):
より強力な電動工具で、錆や塗膜をほぼ全て除去し、金属面を露出させる方法。腐食が激しい場合に用います。

築20年以上経過した設備では、ケレンを「やりすぎる」のも問題です。サビを完璧に落とそうと強力に削りすぎると、腐食で薄くなった鉄板そのものの強度を損ねたり、穴を開けてしまったりする危険があります。 「腐食の状態を診断し、どのレベルのケレンが最適か」を見極められるのが、プロの業者です。
【診断のポイント】
パレットの腐食は、住民の目に見える「表面」よりも、水が溜まりやすく湿気がこもる「裏側」や「端部(縁)」から深刻に進行しているケースが非常に多いです。
見積もり前の現地調査の際、業者が懐中電灯などでパレットの裏側までしっかり確認しているかどうかも、信頼性を見極める一つの材料となります。
錆の処理:「錆転換剤」の使用の有無
ケレンで落としきれない錆(特に錆の根が深い場合)に対して、「錆転換剤」を使用するかどうかもポイントです。これは、赤錆を化学反応で安定した黒錆(不活性な状態)に変え、錆の進行を止める薬剤です。
ただし注意点: 錆転換剤は「活きている赤錆」に化学反応して安定した黒錆に変える薬剤であり、ケレン作業で浮き錆や古い塗膜をしっかり除去することが使用の大前提となります。
表面の錆には有効ですが、深い腐食への効果は限定的です。また、施工後に塗る塗料との相性を確認する必要があります。
「錆転換剤塗布」の記載があれば丁寧な下処理の一環と言えますが、これだけで万全というわけではなく、あくまで補助的な処理として理解してください。
塗装回数:「3回塗り」が基本




塗装は「下塗り・中塗り・上塗り」の3回塗りが基本です。コストダウンのために2回塗りに省略されていないか確認します。
- 下塗り(プライマー): 鉄部と塗料を密着させる接着剤の役割と、錆止めの役割。
- 中塗り: 塗装の厚み(膜厚)を確保し、耐久性を高める役割。
- 上塗り: 美観を整え、紫外線や摩擦から中塗り層を守る役割。
使用塗料①:「樹脂の種類」は適しているか
見積書に「ウレタン塗装」「エポキシ塗装」などと記載されている部分です。特徴を理解しましょう。
| 塗料樹脂 | 特徴 | 耐久性 (目安) |
|---|---|---|
| ウレタン樹脂 | 安価で作業性に優れる。耐候性(紫外線)は標準的。一般的な屋外駐車場で多用される。 | 7~10年 |
| エポキシ樹脂 | 密着性、耐摩耗性、耐薬品性(オイル)に極めて優れる。塗膜が硬い。ただし紫外線にやや弱い。 | 8~12年 |
※重要:これらの年数は理論値(目安)です 実際の耐久性は、施工品質(特に下地処理)、環境条件(屋外/屋内、海沿い、寒冷地など)、使用頻度によって大きく変動します。必ず「目安」として捉え、定期点検で状態を確認することが重要です。

屋外で紫外線が強く当たる場合は「ウレタン」、屋内や地下ピット、オイル汚れが懸念される場合は「エポキシ」が推奨されることが多いです。ただし、従来型の硬質エポキシは硬いため、パレットの「たわみ」に追従できず割れることがあります。近年は柔軟性を持たせた変性エポキシ塗料もあるため、使用される塗料が硬質タイプか変性タイプかも確認しましょう。どちらが最適か、業者に選定理由を必ず確認してください。
使用塗料②:「1液式」か「2液式」か
塗料には、そのまま使える「1液式」と、主剤と硬化剤を現場で混ぜる「2液式」があります。 一般的に「2液式」の方が塗膜が強固で耐久性・耐薬品性に優れますが、高価で、混合の手間や使用可能時間(ポットライフ)の管理が必要です。
【重要】2液式は施工難易度が高い 2液式塗料は、混合比率の正確な管理、気温・湿度による硬化時間の変動への対応など、高い施工技術が要求されます。「2液式ウレタン樹脂塗料」などの記載があれば高品質な仕様と判断できますが、同時に施工業者の技術力が問われることも理解しておきましょう。
使用塗料③:「メーカー名」と「製品名」
NG例:
「ウレタン樹脂塗料 3回塗り」 これでは、どのメーカーの、どのグレードの塗料か分かりません。
OK例:
「下塗り:〇〇ペイント製 エポキシ錆止め、中・上塗り:△△化学製 2液式ウレタンコートX」 ここまで記載されていれば、管理組合側でもその塗料の仕様(カタログスペック)をインターネットで確認でき、信頼性が担保されます。
安全性:「防滑(ぼうかつ)仕上げ」の有無
雨や雪の日に、塗装されたパレットで人が滑って転倒する事故を防ぐため、「滑り止め」の施工は必須です。 「防滑仕上げ」「ノンスリップ仕上げ」といった記載があるか確認します。
防滑処理の主な方法:
- 骨材混入方式:上塗り塗料に「珪砂(けいしゃ/けいさ)」と呼ばれる細かな砂粒を混ぜて、表面をザラザラに仕上げる工法(最も一般的)
- 防滑シート貼付:専用の防滑シートを貼る方法
どの方法が採用されているか、見積書で確認しましょう。
洗浄:「高圧洗浄」の工程
ケレン作業の前後に、高圧洗浄機でパレットに付着した泥、砂、油分、旧塗膜の粉塵を徹底的に洗い流す工程があるか確認します。
特に重要なのが油分(オイルやタイヤワックス)を除去する『脱脂洗浄』です。これが不十分だと、塗料が密着せず早期剥離の原因となります。
高圧水洗いだけでなく、専用の洗剤や溶剤(脱脂剤)を使用するかどうかも確認しましょう。 汚れた面の上から塗装しても、すぐに剥がれてしまいます。
工程管理:「工区」と「養生(乾燥)時間」
工事中の住民の利便性に関わる重要項目です。
- 「工事計画書」や「工程表」が添付されているか。
- 駐車場全体を一斉に止めるのではなく、「Aゾーン」「Bゾーン」など工区を分けて、利用制限を最小限にする計画になっているか。
- 塗装後の「養生(乾燥)時間」が明記されているか。塗装直後は車を載せられません。特に冬場は乾燥に時間がかかるため、夏場より長い養生期間が設定されているか確認します。
【推奨】施工時期の考慮 塗装工事は、湿度が低く、気温が安定する春・秋が理想的です。真夏(塗料の乾燥が早すぎて不均一になる)や真冬(硬化不良が起こりやすい)は避けることが望ましいでしょう。
諸経費:「一式」の中身
見積書の最後に「諸経費 一式」「安全管理費 一式」といった項目があります。 ここには、現場管理費、運搬費、廃材(古い塗膜や錆)の処分費などが含まれますが、あまりに高額(工事費の10%を大幅に超えるなど)な場合は、内訳の提示を求めましょう。
【将来計画編】塗装以外の選択肢も視野に入れる
パレット塗装は、あくまで「延命措置」です。特に、築20年、30年と経過した駐車場では、塗装よりも抜本的な対策が必要な場合があります。
塗装不可能な状態の見極め
以下のような状態では、塗装ではなくパレット交換や装置更新を検討すべきです:
- 鉄板の厚みが著しく減少している(元の厚みの50%以下など)
- 穴あきや亀裂が複数箇所に発生している
- 変形や歪みが目立つ
- 専門業者の診断で「構造強度に問題あり」と判定された場合
判断に迷う場合は、複数の専門業者に診断を依頼し、セカンドオピニオンを取ることをお勧めします。
選択肢①:パレット交換
塗装では追いつかないほど腐食が進行し、鉄板の強度自体が低下している場合は、パレット(またはパレットを構成する一部材)を丸ごと新品に交換する必要があります。塗装よりも高額になりますが、安全性は確実に担保されます。
選択肢②:装置全体の更新(リニューアル)
パレットだけでなく、モーター、ギア、制御盤など、装置全体の老朽化が著しい場合は、塗装や部品交換で延命するよりも、装置全体を更新(リニューアル)した方が、長期的なコストパフォーマンス(ライフサイクルコスト)で有利になる場合があります。
選択肢③:解体・平面化
最も根本的な選択肢です。 「そもそも、機械式駐車場の空き区画が目立っていないか?」「維持費(保守点検費、塗装費)が管理組合の財政を圧迫していないか?」を問い直します。
もし駐車場の需要が減っているのであれば、高額なメンテナンス費用を払い続けるよりも、機械式駐車場を解体・撤去し、アスファルト、コンクリート、あるいは鋼製平面化工法などによる「平面駐車場」にしてしまう方が、管理組合にとって大きなメリットを生む可能性があります。
まとめ
機械式駐車場のパレット塗装は、「塗ればよい」という単純な工事ではありません。 「誰に頼むか」「どのような仕様で頼むか」によって、その後の数年間の安全性と、将来的な修繕コストが大きく変わってきます。
見積書チェックの最終確認リスト
契約前に、以下の項目が明確になっているか最終確認しましょう:
- 下地処理(ケレン)の種別が明記されているか
- 使用塗料のメーカー名・製品名が具体的に記載されているか
- 3回塗り(下塗り・中塗り・上塗り)が確保されているか
- 防滑仕上げが含まれているか
- 工程表と養生時間が明示されているか
- 施工後の保証期間(通常1~3年)が明記されているか
管理会社から提示された見積書を鵜呑みにせず、価格だけで判断しないこと。そして、「安かろう悪かろう」が最も顕著に出る工事であることを肝に銘じてください。
理事会が主体性を持ち、本記事で解説した「下地処理」「塗料の仕様」「工事工程」といった「工事の中身」をしっかりと精査する姿勢こそが、無駄なコストを削減し、居住者の安全とマンション全体の資産価値を守るための、最も確実な第一歩となります。