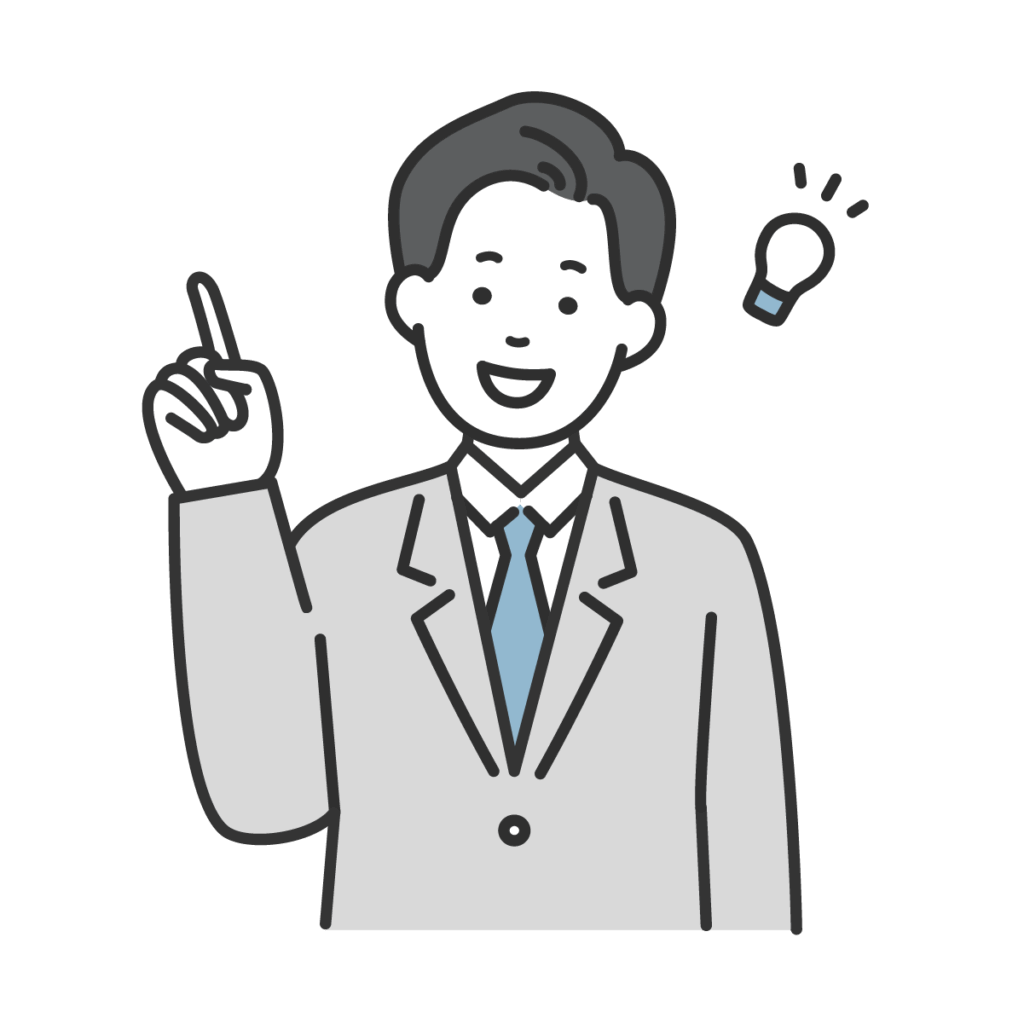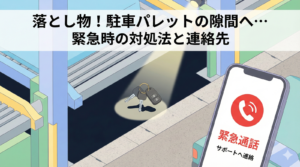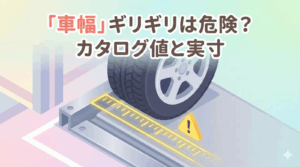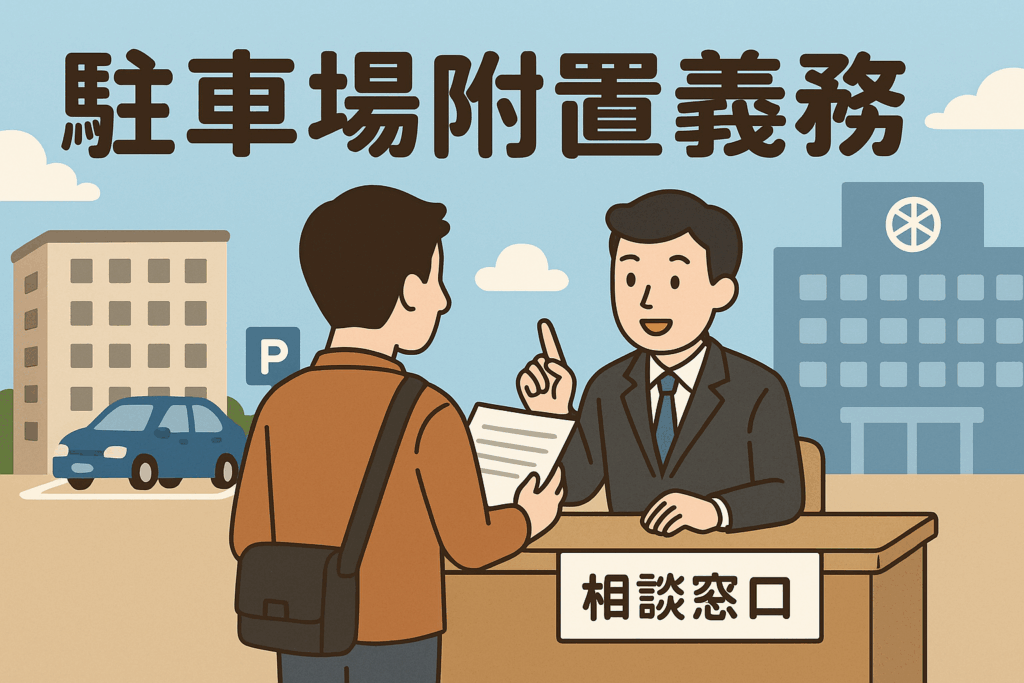
マンションの機械式立体駐車場を解体して平面化する際に、見落としてはならないのが「駐車場附置義務」です。
これは、建物の規模に応じて敷地内に一定の駐車台数を設けるよう自治体が定めた制度であり、解体や平面化によって台数が減る場合には、条例に基づく確認と調整が必要となります。
近年は車離れや空き区画の増加を背景に、各自治体で駐車場附置義務の緩和が進んでおり、状況に応じて平面化が可能になるケースも増えています。
この記事では、駐車場附置義務の基本とその成り立ち、そして全国主要都市における緩和の最新動向を詳しくご紹介します。
駐車場附置義務制度とは?
駐車場附置義務制度とは、都市の一定地域内において、一定規模以上の建物を新築・増築・用途変更などする際に、その建物や敷地内に一定の駐車台数を確保することを求める制度です。とくに集合住宅では、条例により延べ床面積や住戸数に応じた駐車台数の最低基準が定められています。
この制度は、国の「駐車場法」および各自治体が定める「○○市駐車場条例」「○○市附置義務条例」などに基づいており、正式には「建築物に附置すべき駐車施設の附置義務」と呼ばれています。実務では「駐車場附置義務」と略して呼ばれることが一般的です。
なお、これは新築時だけでなく、既存の機械式駐車場を撤去・解体・平面化する場合にも関係してくる重要な制度であり、当時の条例によって定められた附置義務台数を下回る場合には、条例違反となるリスクがあります。そのため、工事計画前に必ず自治体の確認を行うことが推奨されます。
なぜいま駐車場附置義務の見直しが進んでいるのか?
機械式駐車場を所有するマンションでは、「使われていない駐車区画が増えている」「修繕費が高すぎる」「更新費用の見通しが立たない」といった声が年々高まっています。これらは決して一部の特殊な事例ではなく、全国の多くの管理組合が直面している共通課題です。
かつては「駐車場が足りない」時代があり、条例により一定台数の駐車場附置義務が課せられてきました。しかし今では、自家用車を保有しない世帯が増え、空き区画が常態化し、経済的な負担だけが管理組合にのしかかっている現実があります。
こうした背景を踏まえ、駐車場附置義務そのものを見直そうという動きが国と自治体で進んでいるのです。
2018年には国土交通省が「都市再生駐車施設配置計画の活用等による附置義務の適正化について(技術的助言)」を出し、実態に合わない駐車場附置義務を緩和する方向性が示されました。
現在では、東京都や横浜市、福岡市などの多くの自治体が、「空きが多い」「高コストで維持できない」といった事情を考慮し、条件付きで駐車場附置義務台数の削減や解体撤去を認める緩和制度を整備しています。
管理組合が駐車場附置義務の存在を理由に解体をあきらめるのではなく、「今なら現実的に見直せる可能性がある」ということを、ぜひ知っていただきたいポイントです。
出典: 国土交通省 技術的助言 PDF
各都市における駐車場附置義務の緩和動向
東京都のケース
東京都全域
東京都では、「東京都駐車場条例」および「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」により、大規模な建築物の駐車施設の附置が義務付けられています。2019年の技術的助言により、実態に応じた緩和も可能となり、区分所有者の合意があれば、基準台数を下回ることも許容されています。
中央区(東京駅前地区)
中央区では、東京駅前地区(日本橋・八重洲・京橋)において「附置義務駐車施設整備要綱及び運用基準」が設けられ、地域ルール運用組織の承認を得ることで緩和が可能となっています。
出典: 中央区 附置義務駐車施設整備要綱
港区
港区では、駐車場の利用実態に応じて台数削減が可能であり、敷地外(おおむね300m以内)での代替設置も条件付きで認められています。
出典: 港区 駐車場条例について
神奈川県のケース
神奈川県では、「駐車場法」および県条例に基づき附置義務が定められています。緩和判断は市町村単位で行われ、柔軟な対応が可能な場合もあります。
出典: 神奈川県 駐車場法に基づく届出
横浜市
「横浜市駐車場条例」の改正により、地域や建物の用途に応じた緩和が可能となっています。特に横浜駅周辺やみなとみらい地区では、運用面でも柔軟な措置が見られます。
出典: 横浜市 駐車場条例の解説
埼玉県のケース
埼玉県では、「駐車場法」と県の関連条例により附置義務が定められています。市町村レベルで緩和に関する独自運用も可能で、実態に応じた判断が行われています。
千葉県のケース
千葉県では、都市計画区域内の建築物に対して附置義務が課されており、千葉市や船橋市では実情に応じた条例の運用が行われています。
出典: 千葉県 駐車場の整備について
大阪府のケース
大阪府では、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」が存在し、次のような緩和措置が設けられています。
- 敷地外の共同駐車場の利用が認められる
- 緩和承認申請により附置台数の減少が可能
福岡市のケース
福岡市では、2008年2月以降、以下の条件を満たす場合に機械式駐車場の撤去が特例として認められる制度が整備されました。
- 区分所有者の過半が居住
- 設置から10年以上経過
- 総会での合意形成がなされている
- 代替保管場所(平置きなど)が敷地内で確保できる
- 撤去跡地の活用計画(駐車場・駐輪場)がある
出典: 福岡市 附置義務条例について
駐車場附置義務を無視して解体するとどうなる?
私たちの知る限りでは、現在のところ、駐車場附置義務違反により罰則が科されたという明確な事例は確認されていません。
ただし、これは自治体ごとの判断や行政運用によって異なる可能性があり、解体後の用途や申請手続きの不備などが問題となるケースも考えられます。
そのため、駐車場附置義務台数に関する判断や、駐車台数の減少を伴う平面化工事を行う場合は、必ず事前に行政窓口で確認・相談を行うことが重要です。
まとめ
機械式立体駐車場の解体や平面化を進めるには、単なる工事だけでなく、建築時に定められた「駐車場附置義務」の確認が不可欠です。この附置義務は、建物の規模に応じた最低限の駐車台数の確保を求める制度であり、撤去によって基準を下回ると条例違反と見なされる可能性があります。
ただし、国の助言を受けて、各自治体では空き駐車場の増加や維持費の負担を背景に緩和の動きが広がっており、実態に応じた台数削減が可能なケースも増えています。
私たちの知る限りでは、駐車場附置義務違反によって罰則が科された例は確認されていませんが、適切な手続きを踏むことで、解体平面化に向けた管理組合の合意形成もスムースになります。
附置義務の緩和が認められれば、機械式駐車場の解体・平面化を現実的に進められる可能性が広がります。工法の選び方や費用の目安については「機械式駐車場の解体と平面化の基本知識」で詳しく解説しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、条例の運用は自治体ごとに異なる場合があります。最終的な判断や手続きについては、必ず各自治体の担当部署にご確認ください。