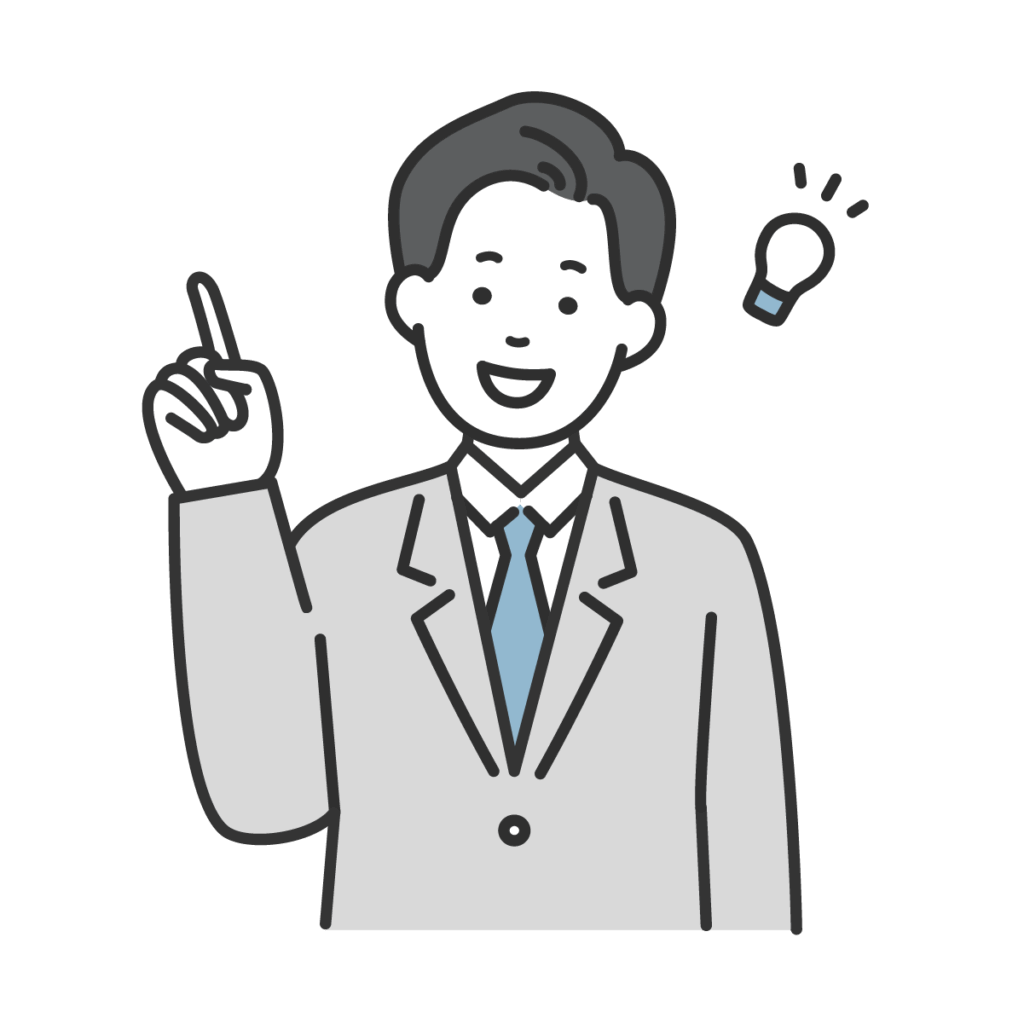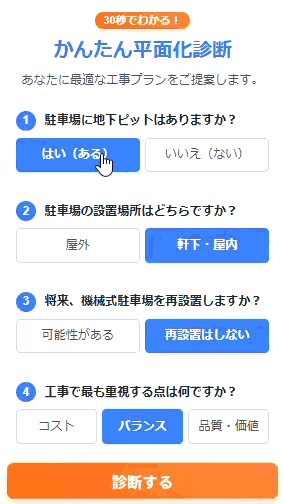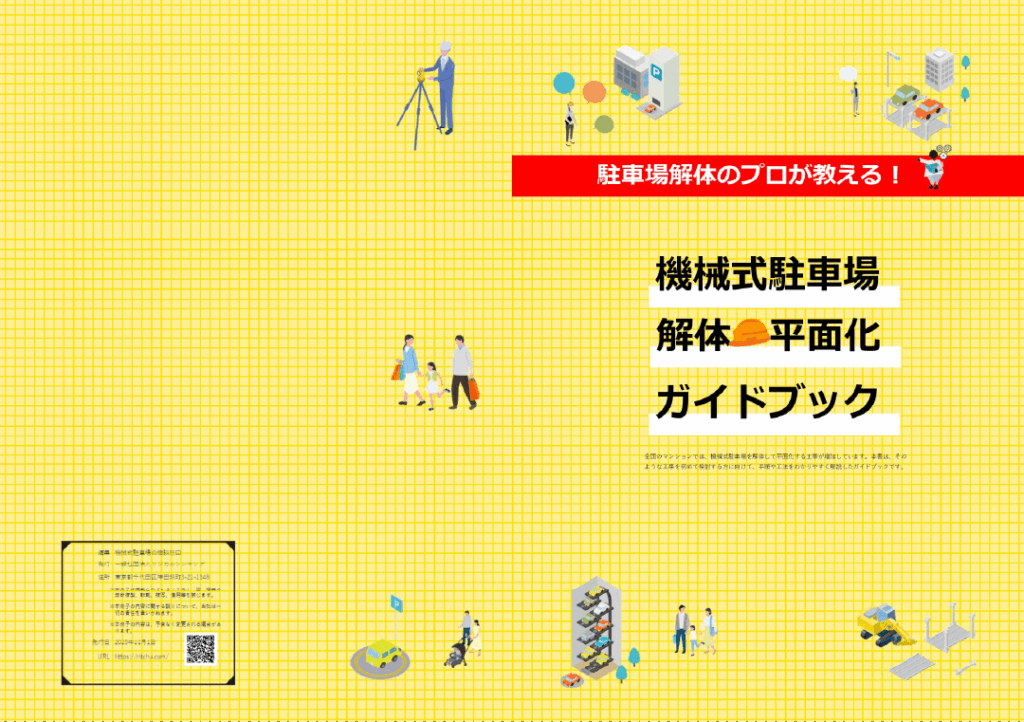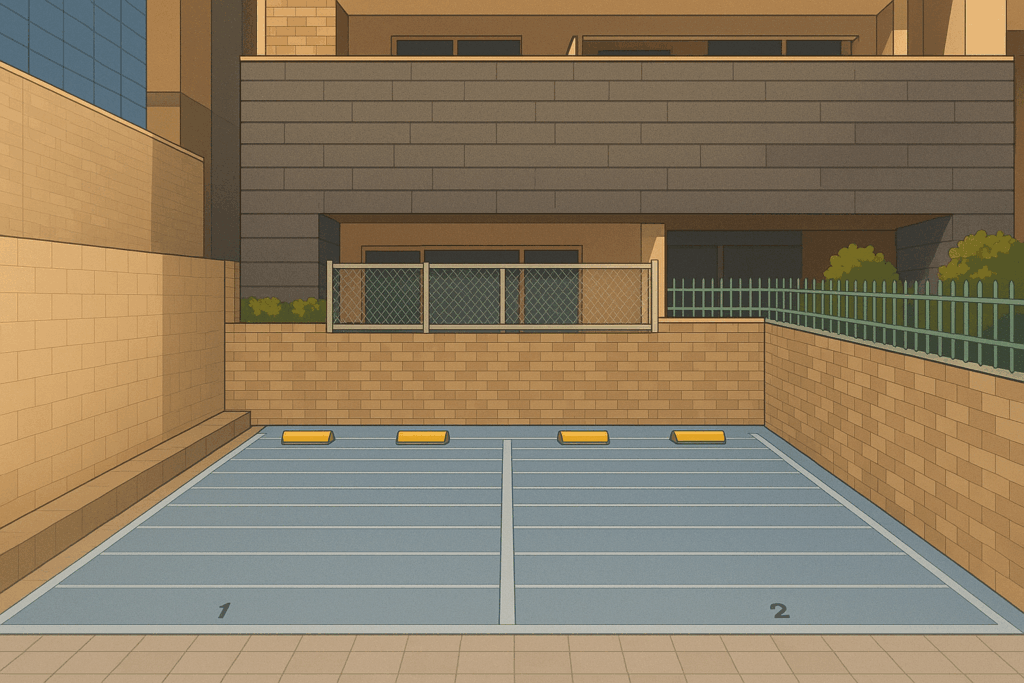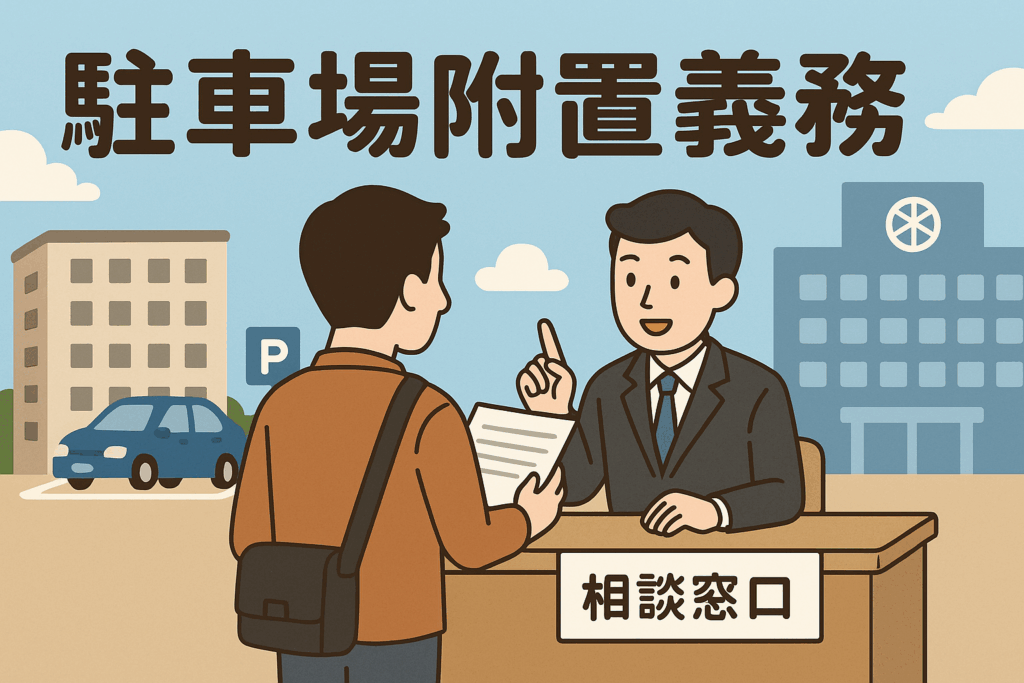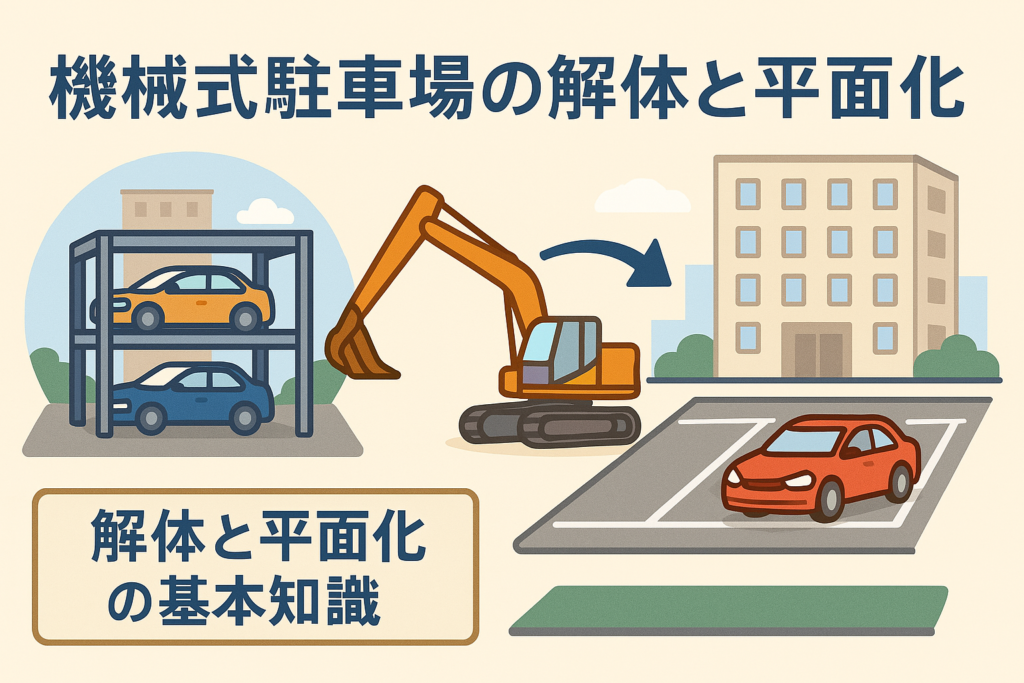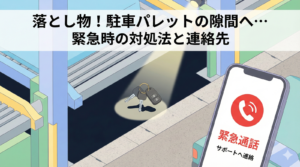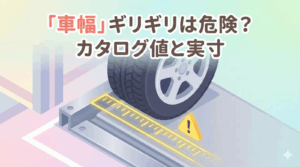マンション管理組合にとって「空き駐車場の問題」は、単に“空いたスペースをどう活用するか”という軽い話ではありません。場合によっては、管理組合の財政そのものに影響を与える大きな課題となることもあります。
特に機械式駐車場では、利用者が減っても点検やメンテナンスの費用は毎月かかり続けます。年間で数十万円にのぼる場合もあり、さらに15〜25年ごとには、数千万円単位の「全体更新(リニューアル)」が必要になることも。まるで“時限爆弾”のように感じている理事の方も多いのではないでしょうか。
こうした「減り続ける収入」と「増え続ける支出」という構造的な問題が、管理費会計からの赤字補填を常態化させ、管理組合全体の財政を圧迫しているケースも珍しくありません。
そこでよく出てくるのが、「空いている区画を外部に貸して、少しでも収益を確保できないか?」というアイデアです。
しかし現実には、法的な手続き、運営上の管理、そして安全面のリスクなど、クリアすべきハードルは少なくありません。思っている以上に慎重な検討が求められるテーマなのです。
管理組合による外部貸し(自主管理)の主な課題
まず多くの管理組合が最初に考えるのが、「業者を介さず、理事会主導で外部利用者を募集して貸し出す」という方法です。
一見すると自由度が高そうですが、これは専門知識も継続性もない輪番制の理事会にとって、“大きな負担”となり、重すぎるのが現実です。
- 募集・契約という「専門業務」
募集広告の作成・掲載、賃料相場の設定、希望者の内見対応、申込者の属性チェック(反社会的勢力でないか等)、そして法的に不備のない「賃貸借契約書」の作成・締結――。これらすべてに専門知識と時間が必要になります。 - 管理・集金という「継続業務」
毎月の集金・入金確認、滞納時の督促、返金処理、そして「機械が動かない」「パレットに入らない」といった24時間体制の苦情対応まで、継続的な実務が生じます。1年や2年で交代する理事会では、引き継ぎが破綻し、運用が長続きしないことも多いのです。 - トラブル対応という「精神的負担」
無断駐車、ゴミ投棄、深夜のアイドリング騒音、敷地内での接触事故――。外部利用者が増えるほど、こうしたトラブルのリスクは高まりがちです。対応一つで他の居住者との信頼関係も揺らぎかねません。 - セキュリティという「最重要課題」
外部利用者にどこまでの立ち入り(エントランス、駐車場)を許可するのか。リモコンキーやセンサータグの貸与・紛失・複製リスクをどう管理するのか。不審者侵入や盗難が発生した場合、管理組合の「管理責任」が法的に問われる可能性もゼロではありません。
このように、外部貸しの「自主管理」は、法務・会計・安全管理のすべてをボランティアである理事会が担う構図になり、実務的には極めて困難と言えるでしょう。
サブリースという選択肢とその実態

こうした煩雑な業務をすべて解消できるように見える仕組みが、「サブリース方式」です。
サブリースとは、管理組合が所有する共用駐車場の空き区画を一括して業者に貸し出し、業者が外部利用者に再貸し(転貸)する仕組みです。管理組合は、実際の稼働率に関係なく、業者から毎月一定の「保証賃料」を受け取れます。
“何もしなくても空き区画が収益を生む”という点で、多忙な理事会にとっては非常に魅力的な「魔法の杖」のように映ります。
しかし、実際にはこの仕組みが「短期的な安心」と引き換えに「長期的なリスク」を内包していること、特に機械式駐車場においては「避けるべき選択」になり得ることを、まずはご理解いただく必要があります。
サブリースに潜むデメリットと保証賃料のリスク
サブリースは、確かに管理の手間を削減しますが、以下のような根本的なリスクを管理組合側が考慮しておく必要があります。
- 居住者との不公平感
サブリース業者は利益確保のため、外部利用者には居住者よりも低い料金で貸し出すのが一般的です。これを知った居住者から「なぜ正規料金を払う自分たちより外部の人間を優遇するのか」と不満が噴出し、理事会への信頼が損なわれることがあります。 - セキュリティ・マナーの悪化
外部利用者は居住者としての責任感を持たないため、敷地内マナー(アイドリング、ゴミ放置、無断通行など)の悪化が起こりやすくなります。部外者の出入りが増えること自体が、居住者の心理的な安心感を低下させます。 - 一方的な「契約リスク」と“減額される”保証賃料
「保証賃料」といっても、未来永劫その額が保証されるわけではありません。地域の駐車場相場の下落や需要減少を理由に、業者から一方的に減額を交渉されたり、契約解除を通告されたりするケースは少なくありません。特に契約更新時には、業者優位の条件変更が行われるリスクがあります。 - 「収益事業」としての税務負担
サブリースによる賃料収入は「収益事業」とみなされ、法人税の課税対象となります。これは、管理組合が「法人格」を持っていなくても同様です。利益が出た場合は、居住者向けの会計とは別立てで「区分経理」を行い、税務申告する必要があります。税理士に依頼すれば、その「税理士報酬」という新たなコストが発生します。
機械式駐車場でサブリースが成り立ちにくい理由
これらのリスクは平置き駐車場でも起こり得ますが、機械式駐車場の場合は、構造的・物理的に、もはや「ビジネスとして成り立たせるのが難しい」レベルの問題が存在します。
最大の理由は、外部利用者に「操作キー」を貸与しなければならないこと。この一点が、あらゆるトラブルの起点になりかねません。
- 誤操作による事故・破損リスク
外部利用者は装置に不慣れです。車両サイズ(重量・高さ・幅)を誤認して入庫させたり、操作ミスでパレットを破損させたりする可能性が高いと言えます。機械の修理費用は数十万円〜数百万円単位になることもあり、その費用負担でトラブルになります。最悪の場合、人身事故に発展するリスクすらあります。 - メンテナンス契約の「対象外」という“爆弾”
これが最も注意すべき落とし穴かもしれません。保守点検会社との契約は、ほぼ間違いなく「居住者による通常の使用」を前提としています。もし不慣れな第三者(外部利用者)が起こした事故や故障が発覚した場合、保証対象外(実費請求)となるか、最悪の場合、保守契約自体を打ち切られるリスクがあります。 - 業者側の“敬遠”と“買い叩き”
サブリース業者もプロです。上記のような高すぎるリスク(事故対応、賠償問題、保険)を熟知しているため、そもそも機械式駐車場を借り上げること自体を避ける(敬遠する)傾向にあります。仮に受けても、その高リスク分をすべて見込んで、管理組合側にとっては「リスクばかり高くて、利益は雀の涙」という極端に安い保証賃料しか提示されないケースがほとんどです。
つまり、機械式駐車場を現状のままサブリースすることは、構造的に成り立たせるのが難しいのです。短期収益を狙って安易に契約すれば、結果的に高額な修理・保険・契約トラブルのリスクを抱え込み、管理組合財政をさらに圧迫してしまう危険性があります。
平面化を前提とした活用転換という選択肢
では、空きが増え続ける機械式駐車場に、もはや打つ手はないのでしょうか。
答えは「いいえ」です。最も合理的かつ持続可能な選択肢があります。 それが、機械式駐車場を解体・平面化し、安全で維持コストのかからない“平置き化”を行った上で、初めて外部貸しやサブリースを検討するというアプローチです。
平面化には「鋼製平面化工法」や「埋戻し工法」などがありますが、どちらの工法でも、これまでの機械的リスクを根本的に解消できます。これは「将来の支出」を抑えるための、賢明な「投資」とも考えられます。
平面化によって得られる3つの主なメリット
- 安全性の抜本的確保
可動部分や操作キーがなくなるため、誰でも安全に利用できます。外部貸しの最大の障害だった「事故・破損リスク」の心配がなくなります。 - 維持コストの劇的削減
機械式駐車装置に関する高額な定期点検費・修繕費・将来的な数千万円規模の更新費が実質的に不要になります。これは、年間数十万円〜数百万円規模の機械特有の固定支出を削減できることを意味し、管理組合の財政はずっと健全になります。 - 資産活用の柔軟化
安全な平置きスペースになれば、サブリース業者も安心して借りてくれます。さらに、「カーシェアリング事業者への貸出」「時間貸しコインパーキング」「EV充電スペースの設置」「バイク置場や駐輪場への転用」など、地域の需要に合わせた多様な活用法を、管理組合が「主導権」を持って検討できるようになります。
まとめ
外部貸しやサブリースは、空き区画の有効活用として魅力的に見えますが、マンションという共同体においては、合意形成・安全管理・税務対応などの課題が伴います。特に機械式駐車場では構造的・法的な制約が多く、現実的にはすぐに収益化を図るのは難しいのが実情です。
まずは平面化を検討し、その上で「どのように活用するか」を考える――。
これが、理事会や管理組合にとって、もっとも現実的でリスクの少ない選択といえるでしょう。